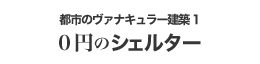
| はじめに ヴァナキュラーvernaculerは、「風土の」「風土に適した」を意味する語である。都市には都市の風土があり、そこに適合した建築は都市のヴァナキュラー建築と呼べるだろう。 そうした視点から都市に見られるヴァナキュラー建築を探っていこうと思う。 スリランカ編:「0円のシェルター」 2004年7月にスリランカに行き、モラトゥワ大学で建築教育の見学をさせて頂いた。 モラトゥワ大学は1985年に建築学部が設立され、現在スリランカで唯一建築学部を持つ大学である。ここでは授業の一環として「0円のシェルター」という非常に興味深い取り組みをおこなっているのでそれを紹介する。 「0円のシェルター」とは、タイトルのごとく0円(ただ)で、使用に耐えるシェルター(仮設建築)をつくるというものである。普通に考えるとただで建物を建てられるわけはないのだが、これには以下のような仕掛けがある。 材料費: 私たちはいろいろな商品に囲まれて都市生活を送っている。商品を買うには当然お金が必要である。しかし、商品の生産過程では必ず商品にならない半端な部分や失敗作も生産される。また、商品は使用された後はただの廃棄物となる。商品を工場から店舗、利用者へ輸送する過程で使用される梱包材はすぐに不要となる。 こうした、生産・消費過程で生みだされる、商品価値のないものに着目すれば、それらはただで入手できるし、いつでもいくらでも入手できる。 もちろん、周囲に自生している自然材を利用しても良い。 建設費: 自分で働けば、ただ。 学生は数人のグループで材料、構法、構造を検討し1つのシェルターをつくる。規模は10平米前後。製作期間は1週間だが、作業をはじめると熱中して皆3日徹夜ぐらいで作品を完成させていた。 設計から建設の一連の過程をおこなうのは、何と入学後2、3ヵ月の学生である。 作品はこのようなものがありました(タイトルは筆者による)。 @ 浮浪(フラー)・ドーム  梱包材の芯になっていたボール紙の筒が構造材。 規格が決まっているので組み合わせるだけでドームができる。 基本となるかたちは五角形と三角形。 隙間に等間隔にヒモを渡しそこに新聞紙をかければ壁ができる(これはどうかと思うが…)。 鴨川の河川敷にでも移植したい出来である。
A 踊るバス停  塩ビパイプを利用した掘っ立てトラス造によるバス停。女学生2人による製作。 屋根にかけた半透明のシートが光を透過してとてもきれい。 シートはロール式で気分に応じて?撤去可能。
B 驚異的な張出しを持つ休憩所   屹立する2本の木柱に支えられ竹の桟敷が斜面に張り出す。 キャンティレバーによる驚異的構造と思いきや木柱はロープで背後の樹木に結びつけられていた。 竹はキャンパス内の竹藪から調達。 荒削りな構造がとにかく豪快で迫力がある。 C 張り子の...  小学生の頃竹ひごで骨組みを作り、そこに新聞紙を貼りニスを塗ってお面をつくったが、その巨大化ヴァージョン。全作品中飛び抜けた軽さを誇る。割竹による自由な造形が面白い。
D 段ボールブロック・ゲート   段ボールをレンガに見立てた、組積アーチ造の水門。確かに段ボールは規格化されており、軽量で強度もある。発想の柔らかさが光る。 くりぬけば採光窓が出来る。 E シェルター?   レンガ、日干しレンガ、竹による混交造の橋。 アーチ部分をレンガ、両岸の基壇を日干しレンガ、上部の床を竹でつくっている。 ここまでゆくと仮設建築とは呼べそうにないが、実際にレンガでアーチをつくってしまう勢いに脱帽である。 F 人類の進歩と調和   大阪万国博覧会における富士グループパヴィリオンを彷彿とさせるエアー・ドーム。 材料は何と製品化前のポリ袋。 内部にはいると水中にいるような錯覚を覚える。 海中を漂うクラゲのようなはかなげな佇まいは生涯忘れることはないだろう。 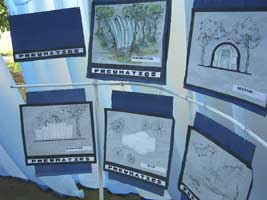 G 折り紙シェルター   段ボールを用いた巨大な折り紙によるシェルター。 同構造の建築作品では横浜国際フェリーターミナルが有名。 しかし、こちらは紙を用いることで伸縮自在な仮設シェルターとなっているところがニクイ。 (ただし、実物大では材料、施工面で再考の余地があり伸縮自在性は捨てられた。)
H 遊牧生活者のための住居   段長手方向に並べた3組のアーチに、両端からテンションをかけたヒモを渡しビニールの覆いをかける。シンプルな構成で、素早く構造的に安定した空間を生み出せる。 繊細な構造的は群を抜いて美しかった。    ディティールも考えられている。 I スバイダー・ハウス  周囲の樹木と地面を構造体とし、そこから紐を張ることで空中に屋根をかけている。 まるで蜘蛛の巣のよう。 屋根は、布を曲線に沿って立体裁断した後、縫い合わせ目止めしてつくられる。 材質は傘に張られる布なので防水性は抜群。
J 番外  土嚢をレンガに見立てて積んでゆくことでも空間をつくることが出来る。 もって行くのは袋だけ、あとは現地で砂を詰めて積むだけという驚異的構法である。 これはアメリカの学生による昨年の作品キャンパス内にひっそりと佇んでいた。 建設時にセメントを混ぜたため解体不能となり殿堂入り。 私の先輩もインド・カッチ地方の地震後この構法で復興住宅を建設していた。 スリランカでは低所得者層の住宅がおおきな問題となっており、 「0円のシェルター」は社会のシステムを視野に入れた実践的取り組みであると(勝手に)得心した。 住民の手でこのような多様な建築が建てられる都市はきっと活気に満ちているに違いない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||